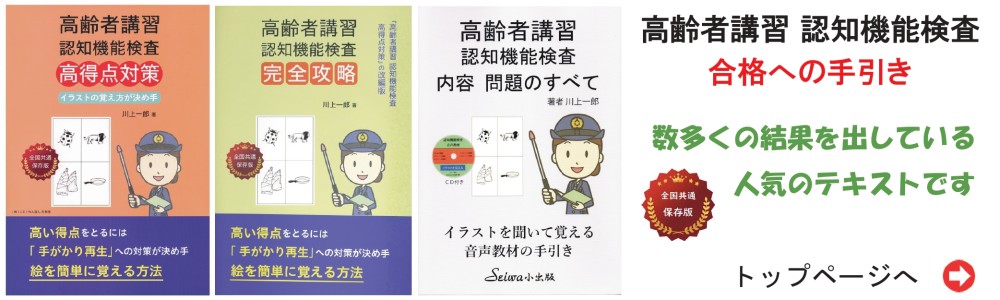それぞれの講習会場によって異なる点もあるとは思いますが、高齢者講習の実施の仕方をお話します。
認知機能検査について
はじめに免許更新日の6か月前になると所轄の警察署から認知機能検査のお知らせのハガキが届きます。
指定された日時の都合の悪い人は早めにハガキに書いてある連絡先に電話をして変更をお願いします。
それぞれ各教室へ分けられ(だいたい5名くらいづつ)、はじめに教官から認知機能検査の内容について説明があります。
タブレットを使用するように変更になったので、年配者の方の中には心配される方がいらっしゃいますが、タブレットが渡されますが、紙に書くと同じように書けばいいだけのことですので、心配する必要はありません。
● 時間の見当識
時計は外さなくてはなりませんので、「今は何時何分ですか?」の記入欄には、事前に検査官が黒板に「只今の時間」と書きますので、それをしっかり覚えておいて、それからだいたいどのくらい時間が経過したかを考えて、およその時間を記入します。
正確でなくても、黒板に書かれていた時刻よりも、「だいたいこのくらい経ったかな」と思う時刻を書けば正解です。
● 「手がかり再生」のイラストを4枚ずつ見せられます。見る時間は1分くらいで、それを4回、計16枚見ます。
しっかり見て覚えておきましょう。無理に全部覚えようとしなくても構いません。自由回答で4枚正解すれば合格ですので。気持ちを落ち着けていれば、普通の認知力であれば4つくらい楽に覚えられます。
● 「介入課題」
イラストの答を書くまでの時間の調整のための課題ですので、間違っても心配いりません。点数には関係ありません。
この課題のときには、さっき出されたイラストを再度思い出すことにした方がいいですね。
● 「手がかり再生」の回答を書きます。
自由回答と、ヒントのある回答の二つに書きますが、はじめに自由回答を書いてから、それを消され、次にヒントのある回答を書いていきます。
自由回答で5つ正解すればあとは書く必要はありませんが、書けるまで書いておきましょう。
私の場合、自由回答の途中で、タブレットにうまく書けなくなってきたので、検査官にペンを取り換えてくれるように言ったら、検査官に「あなたはもう合格ですので、それ以上書かなくてもいいから、合格証を受け取ってお帰りください」と言われました。
タブレットに書かれている答えは、検査官の見ている機器に映し出されているんですね。
36点以上で合格ですので、それ以上の答は必要ないという制度に変わったんですね。
2023年5月の改正までは、時間内に最後まで書いて自分の点数が記入された判定結果の表が渡されていました。
合格した人は合格証が渡されますので、次はその合格証をもって指定された日に高齢者講習へ行きます。
高齢者講習の日はお知らせのハガキが届きます。
高齢者講習
高齢者講習は実車指導とセットで2時間のコースです。
ただし過去3年以内に交通違反をした人は、実車指導ではなく、運転技能検査を受けることになります。
実車指導は運転免許の停止などありません。必ず免許はもらえます。
でも点数はつけられそれに応じてサポートカーや自主返納が勧告されます。
運転技能検査は厳格に点数が査定され、70点以下ですと免許停止になります。
くわしくはこちらのページを参考にしてください。
はじめに教室でビデオを使ったり、指導員の安全運転へのお話があります。
私たち高齢者にとってはこの先安全に車生活を続けていくために大切な内容ですので、決して居眠りなどしないで真剣に聞きましょう。
その後に室内での運転操作技能の体験もあります。そこまで1時間です。
最後に高齢者講習の終了証がもらえますので大切に保管しましょう。
後日免許更新のお知らせのハガキが届きますので、その時この終了証と運転技能検査の合格証と今までの免許証とお知らせのハガキが必要となります。
視力検査が行われ問題がなければ免許が更新されます。
以上高齢者講習 認知機能検査の体験です。